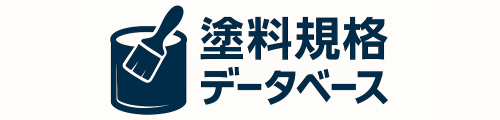塗料とフッ素
この記事の内容
塗料分野におけるフッ素についての記事です。
概要、効能、使用例、樹脂の違い、そしてPFAS規制などについてまとめています。
他サイトであまり解説されていない部分や、塗料と直接かかわる部分を中心に徒然と記載します。
塗料とかかわりない部分の性質や、例えばPFAS規制の概略についてはさらっと流します。
その点ご承知おきください。
フッ素とは
フッ素(F, Fluorine)は、元素記号 F、原子番号 9 を持つ元素です。周期表ではハロゲン元素(第17族)に属し、非常に強い電気陰性度と反応性を持つことで知られています。
基本的に自然界で単体で存在するものでなく、主に蛍石を原料として生産されています。
工業的には、精密電子系の洗浄剤、酸洗い、さまざまな樹脂部品
身近なところでは、虫歯予防、テフロン加工、エアコンなどの冷媒、撥水スプレー、そしてフッ素樹脂塗料などで使われています。
フッ素化合物には無機フッ素化合物と有機フッ素化合物がありますが、塗料で使われるのは有機フッ素化合物です。
塗料とフッ素
塗料におけるフッ素系製品は、2種類 に大別できます。
フッ素樹脂系塗料
フッ素が樹脂の主鎖として機能し、塗膜の主な性能にフッ素が組み込まれた塗料です。
また、アクリル樹脂など他の樹脂の一部にフッ素を化学的に導入して機能性を付与した場合も、化学結合によりフッ素が樹脂構造に組み込まれていれば、フッ素樹脂系塗料ということができます。
フッ素系塗料
フッ素系シランカップリング材を用いた撥水材のように、フッ素をガラスなどの表面に配向させるものや、フッ素系添加剤を樹脂に混合した(結合していない)塗料などが該当します。
これらは「フッ素系塗料」と呼ぶことはできますが、通常はフッ素樹脂系塗料とは言いません。
とはいえ、混合した添加剤であっても実際はある程度樹脂に化学的に結合している場合もあるため、その場合はフッ素樹脂系塗料と見なせるかも……このあたりはケースバイケースです。
フッ素樹脂系塗料の目的
塗料にフッ素樹脂を用いる目的は多くありますが、やはり一番の理由は耐候性でしょう。
耐候性は、簡単に言えば、自然環境下でどれだけ性能を維持できるかを指します。
主には紫外線への抵抗力(耐光性)ですが、それに加えて耐水性や耐薬品性(耐塩水、耐酸耐アルカリ)、耐侵食性(風雨による)などの総合的な指標が耐候性になります。
フッ素樹脂は一般に化学的な結合が強固であるため、この点で非常に優れた特性を持っており、塗膜の長期的な保護や美観維持に大きく貢献します。
また、フッ素樹脂は表面特性を付与する目的でも利用されます。
・撥水性(水をはじく性質)
・撥油性(油をはじく性質)
・摺動性(摩擦を軽減し摩耗防止など)
などが主な機能です。
フッ素樹脂は 耐候性を確保しつつ、また表面機能も付与できる塗料素材として、一般的な外壁から、外装建材、鋼構造物、コンクリート構造物、工業塗装など、多くの塗料に採用されているわけです。
フッ素樹脂の種類
フッ素樹脂にもいくつかの種類があります。
外壁用塗料の説明で、2F、3F、4Fなどの表記を目にしたことがあるかもしれません。
ここでは、それらの違いについて解説します。
先に断っておきますが、ここでは どの種類が優れているか ということは述べません。
これは特定のメーカーへの配慮ではもちろんなく、塗料という単位で考えた場合、フッ素樹脂系塗料の性能は、フッ素樹脂の種類のみで決まるものではないからです。
この点については、少し後に説明します。
まず、塗料分野で使用される2F、3F、4F樹脂については下記のようなものが代表例です。
| 種類 | 樹脂 | 主なブランドとメーカー |
|---|---|---|
| 2F | PVDF(ポリビニリデンフルオライド) | カイナー(Arkema) |
| 3F | FEVE(トリフルオロエチレン系共重合体) CTFE(クロロトリフルオロエチレン) |
ルミフロン(AGC) フルオネート(DIC) ETERFLON(Eternal Cemical) |
| 4F | TFE系 ETFE(テトラフルオロエチレン共重合体) PFA(テトラフルオロエチレン-パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体) FEP(テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体) |
ポリフロン(ダイキン) ネオフロン(ダイキン) ゼッフル(ダイキン) Fluon®ETFE(AGC) |
この2F、3F、4Fは、具体的にはC-Cに対してFが結合している数を示します。(なので、塗料樹脂ではあまり聞きませんが、1Fもあります)
そして、C-F結合はその結合エネルギーの高さから紫外線による破壊が起こりにくいため、フッ素樹脂は優れた耐候性を持ちます。
ならば、4F樹脂の方がC-F結合が多いため強いのではないか――と思えますが、そうではありません。
単純に2F、3F、4Fのみで構成された樹脂は、4Fの方が強い傾向があるといえますが、
実際は、それぞれの塗料樹脂は3Fや4F部分だけでできているわけではないからです。
あくまで、フッ素が結合しているC-C部分の構造に対してフッ素の数が2~4であるのであり、塗料樹脂としてはそれ以外の部分があります。
4FであるTFEをそのままPTFEとしたものは単なるプラスチックであり、塗料にはなりません。
3Fも実際には3F部分とそうでない部分の組み合わせであり、2F(VDF)については単体でも塗料として成立しますが、実際には塗料としての性能(例えば密着性)を確保するため他の樹脂がブレンドされるのが通常ですので、基本的に単体ということはありません。
数だけで言えばHFP(ヘキサフルオロプロピレン)は–CF₂–CF(CF₃)–であり、(Cは3つですが)6Fということもできますし、2Fの樹脂製品であるカイナーについても、VDFとHFPを組み合わせたグレードもあります。
つまり、
Fの数だけ見ても、それだけで樹脂全体が強いかどうかはわかりません。
実際の塗料として見ればなおさらです。
実際の塗料では、耐光性(対紫外線)だけについて言っても、選択されたフッ素樹脂、そのほかのブレンド樹脂、配合量バランス、硬化メカニズム、配合された顔料(特にチタン)、紫外線吸収剤や光安定化剤など、多くの要素が複合的に作用するもので、また、耐光性以外の性能とのトレードオフもあります。
C-F結合が多ければ強い、フッ素樹脂が多ければ強いということは傾向としては言えますが、あくまで一要素にすぎません。
PFASとは
※この項は2025年9月時点での記者知見に基づく情報です。以後の情勢により変化する可能性があります。
先に、PFASとは何かについて解説します。
塗料の話題から離れるため、興味のない方は下部の結論まで読み飛ばしてもらっても大丈夫です。
PFASとは
1.Perfluoroalkyl Substances
炭素鎖(アルキル)上の水素がすべてフッ素(F)で置換された化合物。
構造としては、-CF2-またはCF3を持つもの。
2.Polyfluoroalkyl Substances
炭素鎖(アルキル)上の一部の水素がフッ素(F)で置換されたもの。
構造としては、一部でもC-F結合をもつもの。
のいずれか、または両方を指します。
つまり、この言葉が使われる場合は、文脈によって
1のみ、2のみ、両方
この3パターンに分かれます。(ただし2のみを指す場合はPFASと略すことはあまりないかもしれません)
さらに、これはアルキルと言えるか、長鎖の末端のみ完全置換や、側鎖のみ完全置換をどちらとして扱うか微妙なケースもあり、実際の運用に用いる定義としてはアルキルであるかどうかに拘泥しないことも多いです。
・OECDの定義
PFASs are defined as fluorinated substances that contain at least one fully fluorinated methyl or
methylene carbon atom (without any H/Cl/Br/I atom attached to it), i.e. with a few noted
exceptions, any chemical with at least a perfluorinated methyl group (–CF3) or a perfluorinated
methylene group (–CF2–) is a PFAS.
意訳:少なくとも1つの完全フルオロ化されたメチレン基(–CF2–)または –CF3基を含む(H/Cl/Br/I原子が結合していない)有機フッ素化合物※正確には原文を訳してください
(引用元:https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/07/reconciling-terminology-of-the-universe-of-per-and-polyfluoroalkyl-substances_a7fbcba8/e458e796-en.pdf)

・米国EPAの定義
For the purpose of CCL 5, the structural definition of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) includes chemicals that contain at least one of these three structures (except for PFOA and PFOS which are already in the regulatory process):
1.CF3C(CF3)RR′, where all the carbons are saturated, and none of the R groups can be hydrogen
2.R-(CF2)-CF(R′)R′′, where both the CF2 and CF moieties are saturated carbons, and none of the R groups can be hydrogen
3.R-CF2OCF2-R′, where both the CF2 moieties are saturated carbons, and none of the R groups can be hydrogen
(引用元:https://www.epa.gov/ccl/ccl-5-chemical-contaminants)
意訳:飽和炭素を持つ特定のフルオロ化構造を少なくとも1つ含む化学物質(規制済みのPFOAやPFOSは除く)※正確には原文を訳してください
また、英文ですが、下記のサイトに様々な定義やPFASについての情報がまとめられています。
https://pfas-1.itrcweb.org/2-2-chemistry-terminology-and-acronyms/
ここまで読んでいただければわかると思いますが、正確に言えば、
PFASとは何か、統一された厳密な定義が存在しないのが現状です。ただし、これはあくまで定義による境界線が明確でないというだけの意味であり「明らかにPFASであるもの」は多数存在します。
そこは誤解のないようお願いします。
例えば、
・米国のEPAによるPFASリスト
・自動車関連の業界組織GASGのリスト(GADSL)
などに列挙されているものはPFASと言っていいでしょう。
ただし、後者のリストにはOther PFAS Substancesが挙げられており、
これをリストに掲載されたPFASとして扱うのは自己言及的になってしまいます。
PFAS規制動向
※この項は2025年9月時点での記者知見に基づく情報です。以後の情勢により変化する可能性があります。
規制動向については、塗料の話から離れる事、各国状況が大きく異なること、状況が非常に流動的でありリアルタイム性が重要であるため、この記事では非常に簡単に列挙します。
・PFASのうち、有害性の確認されたPFOA、PFOS及びその塩類は国内においても規制済み。
国内ニュースなどにおいて「PFASが検出された」と言った場合はこれらのみを指す場合も多く、
専門家による解説は存在するものの、現状国内では「PFASが何であるか」も周知が不十分である。
・POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)で下記物資が規制 (2025年5月現在)
長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩,ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド(PFOSF)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html
・「PFOA の分枝異性体又はその塩」及び「PFOA 関連物質」が第一種特定化学物質への指定されている。
https://www.env.go.jp/press/press_03409.html
・あるいは、これらに類するものや包含した物質群についても注目が大きい
PFCAs(PFOAのほか、PFHpA、PFNA、PFDAなど)
PFASs(PFOS、PFHxSのほか、PFHpS、PFNS、PFDSなど)
GenXなど
https://www.env.go.jp/content/000107498.pdf
・企業などが自主的に規制(不使用宣言、撤廃宣言)する例がある。
米マクドナルド(日本経済新聞記事)
良品計画(無印良品)
・海外では日本より規制論が進んでいるが、PFAS全般規制となるかは不透明
EUでは全般的なPFAS規制論が進んでいる(ただし未確定)
米国などでも分野によってPFAS規制が実施されている。
全体として規制方向にはあるが、その範囲や時期については見通しが不明。
・国外であれ、規制されれば日本にも影響はある
輸入(フッ素系原料供給)、輸出製品への規制(フッ素製品の輸出減)
また、二次的な影響(需要減による高騰や廃盤)も考えられる。
・国内参考資料
環境省 「PFAS に対する総合戦略検討専門家会議」「PFASに関する今後の対応の方向性」
環境省 「PFASに関する今後の対応の方向性」 を踏まえた対応状況について
以上、簡単に箇条書きにしました。
PFASと塗料
※この項は2025年9月時点での記者知見に基づく情報です。以後の情勢により変化する可能性があります。
※また、構造が公開されていない製品については一般的な情報からの推測となります。
個別の塗料製品、樹脂製品、添加剤等について、PFASにあたるかどうかは製造者に確認ください。
さて、やっと塗料の話に戻ります。
ここまでの話を踏まえて、塗料において利用されるフッ素がPFASにあたるかを検討します。
定義は……今のところ、一番ポピュラーでわかりやすいOECDの定義を用います。
フッ素樹脂系塗料
1.フッ素が樹脂の主鎖として機能し、塗膜の主な性能にフッ素が組み込まれた塗料
→ほぼPFASです。
2FのPVDFの典型的な構造は-CH2-CF2-であり、PFASの定義に合致します。
3Fや4Fはその構造に確実に-CF2-を含むため、典型的にPFASと言えます。
2.アクリル樹脂など他の樹脂の一部にフッ素を化学的に導入して機能性を付与した場合
→概ねPFASです。
構造が多岐にわたり、また個別に公開されていないため一般論になりますが、機能性付与の為にフッ素を導入した時点で、長短はあるにせよ-CF2-や-CF3は含まれるのが通常でしょう。
非フッ素樹脂系塗料(フッ素系塗料)
3.フッ素系シランカップリング材を用いた撥水材のように、フッ素をガラスなどの表面に配向させるもの
→大体PFASです。
一般的に、基材側にアルコキシ基、表面にフッ素含有官能基が配向されるものであるため、特に撥水目的であれば末端は-CF3でしょう。実際にいくつかの製品の構造を見ても、少なくとも末端は-CF3のようです。
4.フッ素系添加剤
→凡そPFASです。
その多くはフッ素樹脂または界面活性剤であり、構造は公開されていないものがほとんどで推測にはなりますが、フッ素の特性を生かすために添加していることを考えると、親水または親油基が塗膜側、表面にフッ素含有気が配向されると推測されます。これも同様に、少なくとも末端は-CF3であると推測されます。
ということで、ほぼすべてPFASです。仮にPFASが全面的に規制された場合、現行のフッ素をうたう塗料製品はほぼ全滅するでしょう。
建築用塗料分野では、ここ10年程度の新製品などでは、フッ素樹脂塗料の上位グレードとして位置付けた無機塗料のものが多く発売されています。
無機塗料の樹脂が何であるかは一般に明かされないため、フッ素樹脂そのものを避けているのか、フッ素という言葉のみを避けているのかは不明ですが、単純に結合の強さで言えばC-Fが強いということは間違いなく、なかなかどのメーカーも苦慮しているのではないかと思います。
PFASの回避
※この項は2025年9月時点での記者知見に基づく情報です。以後の情勢により変化す
さて、ここで終わっては記事として面白みがないため、一つ考察してみましょう。
PFASに当たらないフッ素利用塗料は成立可能でしょうか。
なお、ここでもOECDの定義を用います。
まずは末端の場合を検討しましょう。
例えば、末端を-CHF₂や–CF₂I、–CF₂Cl, –CF₂Brなど他のハロゲンを結合させたり、あるいはFの一つをOHとすることで、形式的にOECDのPFAS定義を回避可能です。
まず、-OHは安定性が非常に悪いことが想定され、成立可能性が低そうです。
–CF₂Cl, –CF₂Brは、安定性の問題に加え、オゾン層への悪影響が懸念され、現実的ではありません。
となると残るは-CHF₂や-CF₂I ですが、コスト的には-CHF₂がマシでしょうか。
次に、主鎖の場合を検討しましょう。
有力なのが、すでに実在するPVF(ポリフッ化ビニル)です。
この構造は-CH₂-CHF-、つまりフッ素樹脂の分類としては1Fであり、形式的にOECDのPFAS定義を回避可能です。
すでに高耐光性のフィルムとしては製品化されており、2F-4Fには及ばないまでも、フッ素の性能を発揮できる樹脂と考えて良いでしょう。ただし、塗料化できるかは不明です。
では、2Fはどうでしょう。
上に書いたようにPVDFはPFASになりますが、例えば-CHF-CHF-という構造であれば、Cに対しFが一つであり、形式的にOECDのPFAS定義を回避可能です。
しかし、この構造は合成可能性または安定性に疑問があります。というより、この構造が安定し性能を発揮するのであれば、すでにそういう製品があるはずですが、何らかの問題があるのでしょう。
ここまでの結論としては、もしPFAS全てが現在のOECDの定義で規制された際には、PVFや末端-CHF₂のフッ素を使えばいいことになります。
ところで、そもそもPFASの何が問題とされているかというと、分解しにくいことです。
毒性は不明の部分が多いにせよ、分解しにくいことそのものがPFAS規制の本質です。
もし今後毒性が分かったとしても、環境に残存し続けることが問題なのです。
つまり、仮に樹脂の構造を工夫し定義上のPFASを回避したとしても、その十分な耐光性などフッ素の特徴を持っている以上、それはすなわち分解の難しさを意味するため、包括規制が行われる場合は、同じように規制される可能性が高いでしょう。
というオチでした。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
塗料とフッ素の関係について、その性質、目的、種類、そしてPFASについてまとめました。
当サイトの趣旨と違い、具体的な規格と関連する話題ではないですが、塗料にフォーカスを当てた記事があまり見当たらない話題については、今後もこのような記事も書いていく予定です。
免責事項
この記事は記者の調査または経験に基づき、その内容には正確を期しておりますが、
特にPFAS回避の部分は化学素人の思考遊びに近いものです。
「ここ間違ってるよ」「こんな問題が考えられるよ」といったことがあれば、
お気軽にお問い合わせフォームからご指摘ください。
公開日 2025/9/15
最終更新2025/12/7