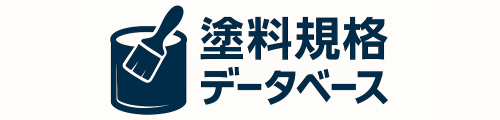JASS18 M-111 水系さび止めペイント
概要
JASS18 M-111は「水系さび止めペイント」についての規格です。
JASSの塗料規格は種類と品質、試験方法などを規定しているもので、用途について規格冒頭に明示していません。
規格名そのもので判断するか、塗装仕様を確認して、それぞれの用途などを把握することになります。
また、品質や試験内容を読むことでも類推は可能です。
しかし、JASS18 M-111は名前がストレートなので、金属下地用の、いわゆる錆止め水系塗料の規格とわかります。
2025年9月(記事作成)時点の最新は建築工事標準仕様書・同解説 JASS18 塗装工事 第8版(2013)であり、詳細な規格の内容は下記をご確認ください。
- 建築工事標準仕様書・同解説 JASS18 塗装工事 第8版(2013) (日本建築学会)
- 建築工事標準仕様書・同解説 JASS18 塗装工事 第8版(2013) (Amazonアフィリエイトリンク)
- 目次プレビュー(日本建築学会)
種類と主な違い
JASS18 M-111 水系さび止めペイントの種類は一つのみです。
品質
この規格は、次の表のように品質を規定しています。
下記は規格より抜粋・変形し引用
| 容器の中での状態 | かき混ぜたとき,堅い塊がなく一様になるものとする. |
| 低温安定性(-5℃) | 変質しないものとする. |
| 塗装作業性 | はけ塗りで塗装作業に支障があってはならない. |
| 乾燥時間(h) | 8以内 |
| 塗膜の外観 | 塗膜の外観が正常であるものとする. |
| 上塗り適合性 | 上塗りに支障があってはならない. |
| 塗膜中の鉛(%) | 0.06以下 |
| 塗膜中のクロム(%) | 0.03以下 |
| 耐複合サイクル防食性 | 36サイクルの試験に耐えるものとする. |
低温安定性は水系塗料ならではの項目です。
またJASS18 M-109と比較すると、乾燥時間が短く設定されていたり、鉛やクロムの規定があったり、耐塩水性でなく耐複合サイクル防食性を定めていたりと、水系にも関わらずやや厳しめの基準となっており、規格自体が比較的新しく作られたという印象を受けます。
すでに存在する規格を大きく変更することは、過去にその規格に該当していた製品が非該当となり混乱を招くため慎重になることがあるようですが、新しい規格を作成する際には、技術向上や要求性能の向上、どちらの面からも品質が厳しくなることはよくあることです。
主な製品
JASS18 M-111 に該当する主な製品は下記の通りです。
| エスケー化研 |
水性エポサビアンダー スマートボーセイW |
| カナヱ塗料 | アルクアマリントップ |
| 関西ペイント | アクアマックスEXⅡ |
| 神東塗料 | 水性デラスト |
| スズカファイン |
水性ラスノンEPO EMエポクール |
| 大同塗料 | アクアコート#500 |
| 大日本塗料 |
アロナEPO アクアマイティーエポ#1000 |
| 日本ペイント |
水性ハイポンプライマー オーデハイポンプライマー 1液水性デクロ |
| 東日本塗料 | 水性サビ止めプライマー |
塗装仕様
JASS18 M-111が必要とされる場面の主なものに、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)および 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)があります。
詳細は以下の仕様書を参照ください。直接該当ページへとリンクしています。
- 公共建築工事標準仕様書 建築工事編(令和7年版)
18 章 塗装工事 3節 錆止め塗料塗り Bs種 Cz種 - 公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編(令和7年版)
7章 塗装改修工事 4節 錆止め塗料塗り Bs種 Cz種
いずれも、屋内仕様となっています。
また、当然ながらJASSの下記塗装仕様にも、JASS18 M-111が記載されています。
- 3節 金属系素地面塗装
EP-G
主として、建築物内部の鋼製または亜鉛めっき鋼製の建具や設備機器などに用いるつや有合成樹脂エマルションペイント塗り
に適用されます。
亜鉛めっきはJASS18 M-111、鉄鋼はJIS K 5674 2種またはJASS18 M-111となっており、いずれも水性の錆止め塗料となります。
A種B種等で塗り回数などが違いますので、詳細は冒頭で紹介した冊子をご確認ください。
なお、JIS K 5674 2種、JASS18 M-111の品質は重複する部分もあり、共に合格としている塗料もあります。ただし、認証品かどうかは別途確認が必要です。
・関西ペイント アクアマックスEXⅡ
・日本ペイント 水性ハイポンプライマー
・スズカファイン 水性ラスノンEPO
などは、少なくとも社内試験ではいずれの基準も合格しているようです。
そのほか、東京都建築工事標準仕様書にもこの規格塗料が記載されています。
深堀り:水系さび止めの品質比較
いわゆる水系さび止め塗料についての規格は、JASS18 M-111のほかにも多くあります。
()内は水系規格が設定または追加された年度です。
・JASS18 M-111
・JIS K 5551 D種 E種(2018~)
・JIS K 5621 4種(おそらく2008~)
・JIS K 5674 2種(おそらく2008~)
・JPMS-21 1種 2種(1989~)
・JPMS-30(2016~)
主なところでもこれだけあります。
下記に品質項目を比較してみました。
項目のみによる比較のため、求められる品質は違う場合があります。
また、厳密には違う項目も、ある程度似た試験項目はまとめています。
例:「防せい(錆)性」と「屋外暴露耐候性」は評価方法などに違いがありますが、
JIS K 5621:2008 防せい(錆)性
JIS K 5621:2019 屋外暴露耐候性
と置き換えられたように、近い試験項目と判断し下記表では同項目。
| 容器の中での状態 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 低温安定性(-5℃) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 半硬化乾燥性 (表面乾燥性・乾燥時間) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 塗装作業性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポットライフ | 〇 | 〇 | 〇 1液を除く |
|||||
| たるみ性 | 〇 | 〇 | ||||||
| 塗膜の外観 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 上塗り適合性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 耐屈曲性 | 〇 | 〇 | ||||||
| 耐おもり落下性 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 付着性(付着安定性) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| フラッシュラストテスト | 〇 | 〇 | ||||||
| 低温造膜性 | 〇 | 〇 | ||||||
| 耐熱性-塗膜の外観- | 〇 | 〇 | ||||||
| 耐熱性-付着性- | 〇 | 〇 | ||||||
| 塗膜中の鉛(%) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 塗膜中のクロム(%) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 耐塩水性 | 〇 | 〇 | ||||||
| 耐複合サイクル防食性 (サイクル腐食性) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 加熱残分 | 〇 | 〇 | ||||||
| 屋外暴露耐候性 (防せい性) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
見ての通り、品質項目にかなり共通部分があることがわかります。
そのため、前の項で記載したJIS K 5674 2種、JASS18 M-111のように、認証を受けるのでなければ、複数の規格を性能面で満たす塗料が成立しやすくなっています。
・設定年度が古く独自の項目があるJPMS-21
・JIS K 5551のたたき台といった性質を持つJPMS-30
・重防食想定でありポットライフ項目がある(つまり通常2液など多液である)JIS K 5551
・屋内を想定しているJASS18 M-111
など、それぞれ違いはありますが、
JIS K 5674 2種とJIS K 5621 4種などは項目がほぼ一致しているため、両方の品質を満たすとPRする塗料もあるようです。
ただし、JIS K 5621はJIS K 5674に該当するものを除いた規格であり、認証としては両立できません。なお、この二つであればJIS K 5674の方がより厳しい環境を想定した規格となっています。
また、そのほかにも
・JPMS32 厚膜形水性有機ジンクリッチペイント
・SDK W-512 水性有機ジンクリッチペイント
などがあります。
ところで、品質を満たすのみでなくJISで認証を受けた水系さび止め塗料となると、該当する製品は極端に少なくなります。またどうやら、過去には認証を受けていたが、今は性能相当品となっている塗料もあるようです。
この状況について確実な理由はわかりませんが、環境対応塗料ということで規格ができた中、各社対応塗料を上市するも、利用場面がそれほど多くないか、あるいはJIS認証品でなくても相当品で通ってしまう、などにより、JIS認証や継続コストを負担するほどのマーケットに満たないか、あるいは性能面で溶剤系に及ばないため結局使用場面が限られてしまう、などと筆者は推測していますが、実際はどうなのでしょうか。
だれか知っていたら教えてください。
免責事項
この記事は記者の調査または経験に基づき、その内容には正確を期しておりますが、
購入や採用などの判断を行う場合は、必ず各規格書及び塗装仕様書の原本を確認し、必要に応じてメーカーに確認してください。
また、「ここ間違ってるよ」「このような塗装仕様でも使うよ」といったことがあれば、
お気軽にお問い合わせフォームからご指摘ください。
公開日 2025/9/8
最終更新2025/10/18