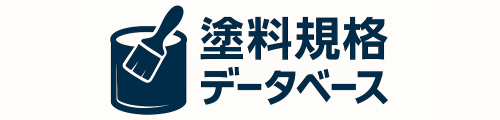JASS18 M-206 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス
(常温乾燥形ふっ素樹脂ワニスおよび常温乾燥形着色ふっ素樹脂ワニス)
概要
JASS18 M-206は「常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス」についての規格です。
JASSの塗料規格は種類と品質、試験方法などを規定しているもので、用途について冒頭に明示していません。
規格名そのもので判断するか、塗装仕様を確認して、それぞれの用途などを把握することになります。
また、品質や試験内容を読むことでも類推は可能です。
JASS18 M-206は名前のみではいまいちピンときませんが、
塗装仕様セメント系素およびせっこうボード素地面塗装 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り(2-FUC)に、
主として,建築物の外部壁面に用いる透明仕上と着色透明仕上げを目的とした常温乾燥型ふっ素樹脂ワニス塗りに適用する
とあります。つまり、現場塗装、セメント系素材へのふっ素樹脂系クリヤーやカラークリヤーということになります。詳しくは塗装仕様の部分で記載します。
2025年9月時点の最新は建築工事標準仕様書・同解説 JASS18 塗装工事 第8版(2013)であり、詳細な規格の内容は下記をご確認ください。
- 建築工事標準仕様書・同解説 JASS18 塗装工事 第8版(2013) (日本建築学会)
- 建築工事標準仕様書・同解説 JASS18 塗装工事 第8版(2013) (Amazonアフィリエイトリンク)
- 目次プレビュー(日本建築学会)
種類と主な違い
JASS18 M-206 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス(常温乾燥形ふっ素樹脂ワニスおよび常温乾燥形着色ふっ素樹脂ワニス)の種類は二つあります。
・常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス
・常温乾燥形着色ふっ素樹脂ワニス
違いも見ての通り、通常品と着色品という違いになります。
塗装仕様を併せて見ますと、透明仕上げと着色透明仕上げとなっており、いわゆるクリヤーとカラークリヤーであることがわかります。
品質
JASS18 M-206は、次の表のように品質を規定しています。
下記は規格より抜粋・変形し引用
| 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス | 常温乾燥形着色ふっ素樹脂ワニス | |
| 透明性 | 透明であるものとする. | 見本品と比べて同等の着色であり,透明であるものとする. |
| ポットライフ | 5時間で使用できるものとする. | |
| 塗装作業性 | 吹き付け塗りで塗装作業に支障があってはならない. | |
| 乾燥時間(h) | 16以内 | |
| 塗膜の外観 | 塗膜の外観が正常であるものとする. | |
| 耐水性 | 水に浸しても異常があってはならない. | |
| 耐アルカリ性 | アルカリに浸しても異常があってはならない. | |
| 屋外暴露耐候性 | 24か月の試験でふくれ,割れ,はがれがなく,見本品に比べてつやと色の変化の程度が大きくないものとする. | |
| 樹脂分中のふっ素の定量% | 15以上 | |
この内容から、
・ポットライフがあることから、2液(多液)の塗料
・屋外暴露耐候性が24か月であることから、ある程度耐候性を期待する外壁用塗料
ということがわかります。
・樹脂分中のふっ素の定量%
という、ちょっと珍しい項目がありますが、これについては後ほど触れます。
ところで、ワニス系は「容器の中の状態」の項目がないのはなぜでしょうか。
主な製品
JASS18 M-206 に該当する主な製品は下記の通りです。
通常はここに当サイトの検索リンクと製品リストを掲載するのですが、
該当塗料が一つも見つかっていないため、検索にこの項目自体が存在しません。
過去には該当塗料が存在し、最近では日本ペイントの設計価格表 2023年5月版に
常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス :デュフロン4FⅡプーレスーパーフレッシュクリヤー
常温乾燥形着色ふっ素樹脂ワニス:デュフロン 4F Ⅱプーレスーパーフレッシュカラークリヤー
がそれぞれ2種類の規格に該当することが掲載されていますが、設計価格表 2025年9月版では掲載されていません。
これは直接的には2024年に日本ペイント社の4Fシリーズが終了しDFシリーズにリニューアルしたことの影響と思われます。
・ニュースリリース
建築用分野「DFシリーズ」からリニューアル発売開始 ~次世代フッ素樹脂塗料「ファインDFセラミック」・ 「ピュアライドUVプロテクトクリヤーシリーズ」~
しかし、JASS18 M-206の適合品はリニューアルされていないようです。
塗装仕様
JASS18 M-206の記載がある仕様として、
JASS18
セメント系素およびせっこうボード素地面塗装
常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り(2-FUC)
があります。
主として,建築物の外部壁面に用いる透明仕上と着色透明仕上げを目的とした常温乾燥型ふっ素樹脂ワニス塗りに適用する。
としており、塗装種別は
・A種 下塗り1回/中塗り2回/上塗り1回 計4回塗り
・B種 下塗り1回/中塗り1回/上塗り1回 計3回塗り
の2種で、すべて同じ種類の塗料を使用し、塗り回数が違うのみです。
適用下地は
・コンクリート
・セメントモルタル
・プレキャストコンクリート部材
となっています。
塗装方法は
常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス :はけ塗り、ローラーブラシ塗り、吹き付け塗り
常温乾燥形着色ふっ素樹脂ワニス:吹き付け塗り
となっています。
工程表を見ると、工程間隔がすべて16h以上7d以内となっており、素地調整を含まず、この塗料を塗る作業だけでA種はまる4日、B種はまる3日かかります。
ただし、吹付け塗りの場合は工程間を5時間以上とできるとも定めており、その場合は、A種B種とも2日かかります。
このような塗装仕様の工程表では、一般的なメーカーの塗装仕様に定める所要量でなく塗付け量で規定されているため、それを厳守する場合、
・刷毛塗りは3-4日かかる
・吹付け塗りは2日で終わるが必要な塗料の量がかなり増える(ロスが大きい為)
となり、厳しい2択を迫られますことになります。
なお、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)および 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)にはJASS18 M-206を指定した仕様はないようです。
深堀り①:ワニスとは何か
「常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス」
この規格名を解釈していきます
常温硬化形:
この規格はポットライフが定められているため、反応硬化形との対比としてでなく、
焼き付け硬化形や紫外線硬化形との対比でしょうか。低温硬化形との対比かもしれません。
フッ素樹脂:
フッ素系の樹脂です。
フッ素樹脂については、塗料とフッ素で分類していますのでご一読ください。
定義としては部分的にフッ素を導入した樹脂も含まれますが、
この規格ではフッ素15%以上を定められているため、一定以上フッ素が主である樹脂を指すものと考えられます。
ワニス :
本来、乾性油をメインとした塗料、いわゆるニスを指しますが、
JIS K 5500ではそれを油ワニスと定めています。
一方、ワニスについては
樹脂などを溶剤に溶かして作った塗料の総称。顔料は含まれていない。
塗膜は概して透明である。
とかなり広く定義しており、一般的に溶剤形クリヤー塗料をさします。
(溶解の定義にもよりますが、NADは含まれないかもしれません)
油ワニスとフッ素樹脂の組み合わせはあまり一般的でないので、
この規格においては、JIS定義と同様であると考えられます。
つまり
「常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス」
とは、「現場塗装用の使うフッ素樹脂メインのクリヤー塗料」ということになります。
余談ですが、塗料製造などにおいては、JIS K 5500よりもさらに広く、
顔料を混ぜる前の中間体をワニスということがあります。
場合によってはNADや水性エマルジョンも含み、クリヤーの担体を指す言葉として使われます。
一方、場合によっては厳密に油ワニスを指す場合もあり、
かつそれぞれの文脈で排他的(通常は両方を含めることはない)ですので、注意が必要です。
深堀り②:ふっ素の定量について
品質に、「樹脂分中のふっ素の定量%」という項目があります。
現在、「フッ素樹脂塗料」というと、一般的にフッ素の含有量が問われることはありません。
是非はともかく、ほんの少しでもフッ素が入っていればフッ素樹脂塗料と言えます。
その意味でもちょっと珍しい項目なので、詳細を見てみましょう。
樹脂分中のふっ素の定量
樹脂分中のふっ素の定量は,JIS K 5658 の 4.15(主剤の溶剤可溶物中のふっ素の定量)の該当する項目と方法による.ただし、遠心分離器による固形物の分離は必要としない.
このように定められています。
しかし、
JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料
については上記に解説記事を書いていますが、現時点での最新版JIS K 5658:2010に、
主剤の溶剤可溶物中のふっ素の定量という項目はありません。
試験項目も7.1~17に定められており、4.15は存在しません。
とはいえもちろん、JASS18の参照先が存在しないなどということはなく、
これは過去のJIS K 5658の試験項目です。
日塗検ニュース 2010
p17 塗料関係JIS 制定・改正の動向-JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料の改正について-
を参照すると、JIS K 5658:2002からJIS K 5658:2010への改定時に、
成分規定から性能規定へと変更されており、「フッ素の定量」が削除になっています。
また記事中にもありますが、JIS K 5659もその2年前に全面改定されており、
これは下記の大日本塗料の資料でも触れられています。
重防食塗装系の耐候性に関する変遷~重防食塗装系の上塗りが担う使命~
DNTコーティング技報No.18 2018年10月発行
鋼構造物塗装上塗りに用いられる塗料用JIS規格は、2008年に大きな変更がなされている。これまで材
料規格であったJIS K 5657鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料(2002年)とJIS K 5659鋼構造物用ふっ素樹脂塗料(2002年)が統合され、JIS K 5659鋼構造物用耐候性塗料(2008年)として性能規格化された。材料規定から性能規定に変更されたことにより、材料規定の1つであったJIS K 5657(2002年)記載のNCO基の定性の表記や、JIS K 5659(2002年)記載の主剤の溶剤可溶物中のふっ素の定量(%)は記載がなくなった(表3)
これらの状況から、JASS18 M-206の品質試験方法に定められたJIS K 5658 の 4.15(主剤の溶剤可溶物中のふっ素の定量)は、JIS K 5658:2002を指すものと考えられます。
さて、記事冒頭に示した通り、JASS18 の最新は8版(2013)です。
つまり、2013年に出版された規格で、当時最新の2010年のJIS K 5658でなく改定前の2002年の試験方法を参照しており、かつその明示(JIS K 5658:2002と記載)もしていないことになります。
この理由までは分かりませんでしたので、ここからはあくまで想像になりますが、
JASS18 M-206はこの時点ですでにほぼ商品も少なく、仕様が採用されることも多くはなく、改定時の注目度が低かったのではないでしょうか。
とはいえ、適合塗料が存在しており積極的に廃止するまでもない、微妙な立ち位置であったのかもしれません。
あるいは、単純に記載ルールとしてJISの年度を指定しないことになっているのかもしれません。
なお、首都高速道路株式会社の規格
土木材料共通仕様書(平成29年2月)
SDK P-434 低汚染形ふっ素樹脂塗料(上塗)
の品質項目に「主剤の溶剤可溶物中のふっ素の定量 %」が定められています。
平成29年、2017年でJIS改定後のため、その試験方法も詳細に示されています。
深堀り③:クリヤー塗料の規格について
実は、耐候性が求められるクリヤー塗料の規格というのは、やや珍しいのが現状です。
単にクリヤーでも可能というだけであればシーラーなどが規定されていますが、
記者の知る限りクリヤーが前提のJISはなく、JASS18においてもM-206のほかは、
同じくワニスであるM-502、M-203、M-205、そしてJASS塗装仕様のM-307くらいでしょうか。
いくつか理由がありそうですが、一つ思い浮かぶことがあります。
コンクリートやモルタルに溶剤形フッ素樹脂系のクリヤー塗料を塗装すると、とても濃い色になります。(いわゆる濡れ色、コンクリートやモルタルを水で濡らしたときの色です)
これは基材表面の細孔を塗料樹脂が埋めて光を吸収してしまうためです。
塗膜そのものはクリヤーのためクリヤー塗料には間違いないのですが、
どのみち色を変えてしまうなら最初からエナメル塗料を使えば耐候性も確保できるため、
実際の見た目を元の色と大きく変えてしまうクリヤー塗料は、なかなか使いどころが難しいかもしれません。
免責事項
この記事は記者の調査または経験に基づき、その内容には正確を期しておりますが、
購入や採用などの判断を行う場合は、必ず各規格書及び塗装仕様書の原本を確認し、必要に応じてメーカーに確認してください。
背景ハイライト部はその直前に示した資料からの引用となります。
また、「ここ間違ってるよ」「このような塗装仕様でも使うよ」といったことがあれば、
お気軽にお問い合わせフォームからご指摘ください。
公開日 2025/9/21
最終更新2025/10/18