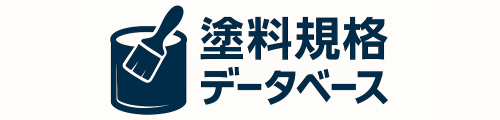はじめに
塗料に関する規格には、大きく分けて「試験の規格」と「品質や規格(製品規格)」、そして「塗装の規格(塗装仕様)」があります。
- 試験規格:試験や判定の方法を定めたもので、試験条件や測定手順を標準化したもの。
- 品質規格:複数の項目について、試験方法や品質基準を定めたもので、最終的な製品の性能を規定したもの。
- 塗装規格:どういった塗料を使うか、どのように塗るかなど塗装仕様を定めたもののなかで、塗料メーカー以外が規定したもの。
塗料についていえば、JISは試験規格と製品規格、JASSは品質規格と塗装規格が含まれますが、当サイトでは主に「製品規格」を対象としています。
どのような規格があるのか
塗料分野でよく用いられる規格は下記のようなものがあります。
現在、当サイトの検索では上から4種に対応していますが、それ以外の規格についても適宜対応予定です。
| 規格図書名または規格名 | 通称または略称 | 発行 | 図書 |
|---|---|---|---|
| 日本産業規格 | JIS | 一般財団法人 日本規格協会(JSA) | 公式サイト |
| 建築工事標準仕様書 | JASS | 一般社団法人日本建築学会 | 販売 / Amazon |
| JWWA規格目録 | JWWA | 公営財団法人日本水道協会 | 販売 |
| 日本塗料工業会規格 | JPMS | 一般社団法人日本塗料工業会 | 販売(一部は無償公開) |
| コンクリート標準示方書[規準編] | JSCE | 公益社団法人 土木学会 | 販売 / Amazon |
| 鋼道路橋防食便覧 | 便覧 | 公益社団法人日本道路協会 | Amazon |
| 鋼橋塗装設計施工要領 SDK | SDK | 首都高速道路株式会社 | 販売 |
| 土木工事共通仕様書関係基準 塗料規格(HDK規格) | HDK | 阪神高速道路株式会社 | 公開 |
| 塗装設計施工基準 | NES | 名古屋高速道路公社 | 販売 |
| 構造物設計基準・塗装補修基準 | FKD | 福岡北九州高速道路公社 | 公式サイト(要問合せ) |
| 構造物施工管理要領 | NEXCO | NEXCO(東日本・中日本・西日本高速道路株式会社) | 販売(令和6年版) / 販売(令和7年版)※2025/07/30時点準備中 |
| HBS塗料規格 | HBS | 本州四国連絡高速道路株式会社 | 公式サイト(要問合せ) |
| 鋼構造物塗装設計施工指針 | SPS | 公営財団法人鉄道総合技術研究所 | 販売(2025/7/29時点在庫切れ) |
| 土木材料仕様書 5章 塗料 | 東京都建設局規格 | 東京都建設局 | 公開 |
| 防衛省仕様書 | DSP | 防衛装備庁 | 公開 |
※本ページのAmazonリンクはアフィリエイトリンクを使用しています。
どのような時に規格塗料が必要か
「多くの(本当に多くの!)塗料の選択肢がある中、何故規格塗料が必要なのか。
品質が保証されていて安心だから」「目的の性能を得るのにこの規格品であれば間違いない」「何の規格もないものに比べて信頼性が高い」なども理由ではありますが、その他にも大きな理由があります。
それはズバリ、「使うよう指定または推奨されているから」です。
たとえば設計図書に「この規格製品を使用すること」と書かれていれば、塗装はそれに従う必要があります。
もちろん、使うよう指定するのには根拠があります。
それがつまり、冒頭の「塗装の規格(塗装仕様)」です。
例えば、下記のような国土交通省の公開している文書です。
公共工事、例えば市区町村の庁舎や図書館などの建築工事では、公共工事建築仕様書に従い「この素材についてはこの規格品を塗って……」と決められます。その自治体の仕様がある場合もあります。
また、 先程の表のように、首都高速道路株式会社の橋梁塗装で案件で塗装工事を行うなら、「土木工事共通仕様書関係基準 塗料規格」に適合する製品を使う必要があります。
自治体では例えば東京都が下記のような仕様を明示しています。
また保険や建材メーカーなどが規格塗料を推奨する場合があります。
これらを根拠に、規格塗料が必要になってくるわけです。
規格塗料は高性能なのか
余談ですが、こんなに公共工事などで指定されている規格品だから、性能も間違いなく高い……とは限りません。もちろん、低いという意味ではなく、最新・高級グレードとは限らないという意味です。
規格品とは、「ある一定の性能基準を満たしていると確認されている」という製品です。
しかし、その性能基準の値そのものはなかなか大きく改定されません。(大きく改定されると、すでに取得している商品は全てやり直しが発生して大変です)
そのため、数字の基準が十年以上(ものによってはもっと)昔のものであったりするので、当時は最高グレード品質であった基準を、現在は中程度のグレード品が満たしていたりします。
またたとえば、あるメーカーが既存の規格品を改良してより高性能なものを開発したとしましょう。
しかし、JIS規格品の配合などを大きく変更するにも、新しく規格を取得するにも、費用や手間がかかります、ならば、高性能なものは規格を取得せず新しい商品として販売したほうがいいか、となる場合があります。
そうなると、規格指定がある場合は古い製品(規格取得済)を販売し、ない場合はより性能の高い製品(未取得)を別製品として販売するということになります。
そんなわけで、指定がない時はより良いものを選ぶ、という選択肢もある訳です。
もちろん、一部にそういう例があるというだけで、全てについて言えるものではなく、規格品より高性能な製品が開発されてない場合も多くあります。
枯れた技術というのは重要です。
規格「認証」「取得」「適合」「準拠」「合格」「相当」は何が違うのか
よくカタログで見かける言葉ですが、例えばJIS(日本産業規格)に関しては、次のように見ておけば大体は間違いないでしょう。
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| 認証・取得 | 指定の認証機関によって正式に認証された製品。製品にJISマークや認証番号がついています。 |
| 相当・準拠 | メーカー内部の試験、または第三者機関の試験でJIS基準を満たすと判断しているが、認証は取っていない。 |
| 適合・合格 | 認証品をこのように書くこともあれば、相当品をこう書く場合もあります。ややこしい。 |
しかし、こういった表記は明確な基準がないため、メーカーによって表記方法が変わります。カタログには規格名しか書いてない場合も、認証品だったり相当品だったりします。
なので、規格品が必要な場合は、必ずメーカーや販売店への確認が必要です。
JIS以外の規格ではどうか
JISのほか、JWWAのように認証が必要なものもありますが、性能を満たしていれば名乗れる、というものもあります。しかしその場合も、実際の採用にあたっては以下のようなパターンがあります
- メーカーの自社試験のみでよい場合
- 必ず第三者機関による試験が必要な場合
- 抜き取り検査がある場合
「自己申告でOK」「試験結果が必要」「実際に製品チェックが行われる」と、いろいろなケースがあるわけですね。
それ以外の塗料関連の規格といえば……
建築分野(主に内装)でよく見かけるのが
- F☆☆☆☆(フォースター)
- 防火材料(不燃材料・準不燃材料・難燃材料)の認定
これらは国土交通省が関与する制度で、内装制限などにも関わる、非常に重要な基準です。
これはむしろ建材などが中心の制度ですが、塗料も該当します。しかし、塗料については建材とはまた違う事情がいろいろあって……この話は少し長くなりそうなので、別記事で解説しました。
そのほか、バイオマス(日本有機資源協会認定)などもあります。
これについては今後また記事追加するかもしれません。
おわりに
塗料に関する「製品規格」は、試験方法や性能基準を共通化することで、施工や製品選定の指針となる基準です。JIS規格をはじめ、さまざまな規格が存在します。
また、認証や適合、相当といった表記にのゆれもあるため、実際にJISマークがあるかどうか、第三者試験の有無などをメーカーに確認することが必要です。
記事にあるように、規格品=常に現在の高性能品というわけではありませんが、一定の品質が保証されているからこそ、信頼性の重要な工事においては欠かせない存在です。
免責事項
この記事は記者の調査または経験に基づき、その内容には正確を期しておりますが、
「ここ間違ってるよ」「こんな規格もあるよ」といったことがあれば、
お気軽にお問い合わせフォームからご指摘ください。
公開日 2025/7/30
最終更新2025/10/6