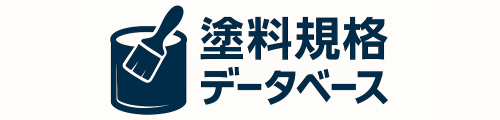はじめに
防火材料認定は、特に施設や内装などで非常に重要な規格です(内装制限)。この規格を持った塗料でないと使用できないケースも少なくありません。
種別が少なく製品数が多いため、当サイトの検索機能には対応していませんが、せっかく規格を扱うサイトですので、簡単に解説しておきます。
防火材料認定とは
塗料における防火材料認定は、不燃(材料)認定とも呼ばれ、性能を満たしたうえで国土交通大臣の認定を受けた材料を指します。
単に性能を満たすだけでは「防火材料」とは呼べません。
主な分類(外部仕上用を除く)
| 分類 | 認定対象 | 認定記号 |
|---|---|---|
| 防火材料 | 不燃材料 | NM |
| 準不燃材料 | QM | |
| 難燃材料 | RM |
この3種類の違いは「燃えにくさ」です。
- 不燃材料 :20分の燃焼試験で合格
- 準不燃材料 :10分の燃焼試験で合格
- 難燃材料 : 5分の燃焼試験で合格
20分試験に合格した場合は、3種すべての認定を受けられます。
建築塗料分野では、「不燃材料」認定、つまり3種全てを受けているものが多く、
「準不燃認定」「難燃認定」のみというものはあまりありません。
ちょっと細かい話-塗料と防火認定の関係-
実は塗料そのものが防火材料として認定されるわけではありません。
認定を受けるのは「不燃材料に塗装された状態」です。
具体的に言えば、以下のような条件で認定されます。
- 定められた不燃材料の上に
- 認定範囲内の不燃材料を選び
- 認定された塗り方(組み合わせ・塗布量や膜厚)で塗る
① 定められた不燃材料
具体的には以下の17種類です(建設省告示第1400号)。
一 コンクリート 二 れんが 三 瓦 四 陶磁器質タイル 五 繊維強化セメント板 六 厚さ3mm以上のガラス繊維混入セメント板 七 厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 八 鉄鋼 九 アルミニウム 十 金属板 十一 ガラス 十二 モルタル 十三 しっくい 十四 石 十五 厚さ12mm以上のせっこうボード 十六 ロックウール 十七 グラスウール板
これら以外は基材としての不燃材料に該当しません。
例えば木はここに示された不燃材料ではないので、「木に塗る塗料で木に塗った場合の防火認定を取る」ということはできません。
これは不燃木材(準不燃や難燃の認定を取っている木材)を基材とした場合でも同じです。
ただし、これは塗料製品として売る場合に認定をうけられないという事であって、
「木に塗料を塗った『燃えない木』という建材で防火認定を取る」ことは性能を満たせば可能です。
② 認定された範囲
認定書に記載された基材に限られます。例えば「金属板を除く」とあれば、鉄鋼・アルミ・金属板は対象外です。
なお、一つの認定書で17種類すべての認定を受けることはできない……はずです。
③ 認定された塗り方
下塗り・上塗りの組み合わせや塗布量(膜厚)が規定され、これを逸脱すると認定外になります。
例えば、塗りすぎて認定書の範囲を超えると認定範囲外になります。
これらの具体的なことが記載されている認定書については、個別にメーカーから取り寄せる必要があります。
もうちょっと細かい話-たまにある誤解-
塗料の防火認定は、たまに「塗膜が燃えない」「塗料を塗ると基材が燃えなくなる」と捉えられる場合がありますが、一般的にはそのような意味ではありません。(そういった製品も存在しますが、ごく一部の例外です)
誤解を恐れずに言ってしまえば――合成樹脂が含まれる塗料は、基本的には燃えます。(例外あり)
多くの場合は、「燃える成分が少ない」ということであり、これは先ほどの、認定以上に塗ってはダメ、という話に繋がります。
もし塗料が基材を燃えなくするのであれば、塗れば塗るほど性能が上がるわけですから、むしろ「これ以上塗りなさい」となるはずですが、実際は上限が決まっているのが通常です。
さらに細かい話-認定の確認や取得について-
防火認定は国土交通大臣認定であり、下記のように公的に公開されています。
この表を「塗装」で検索して出てくるものが、塗料製品または塗料を塗った建材です。
「塗料そのものが防火材料として認定されるわけではない」ということをお分かりいただけるかと思います。
表にあるように、性能評価は以下の機関で行われます。
(それぞれ防火材料関連のページへのリンク)
また、塗料分野の防火材料認定ではこのリスト以外に、下記のような認定番号があります。
代表として不燃認定番号のみ記載します。
- NM-8585 … 日本塗料工業会 が取得し、会員メーカー製品に適用
- NM-8571 / NM-8572 / NM-8573 … 日本建築仕上材工業会 が取得し、会員メーカー製品に適用
おわりに
簡単に解説と書きましたが、少し細かい話が多くなってしまいました。
一般的な建材等の防火材料認定については解説が多く存在しますが、塗料に特化した詳細な情報は少ないため、すこし掘り下げてみました。
皆様の参考になれば幸いです。
免責事項
この記事は記者の調査または経験に基づき、その内容には正確を期しておりますが、
「ここ間違ってるよ」「こんな規格もあるよ」といったことがあれば、
お気軽にお問い合わせフォームからご指摘ください。
公開日 2025/8/2
最終更新2025/9/30