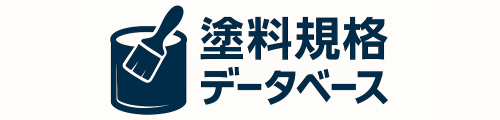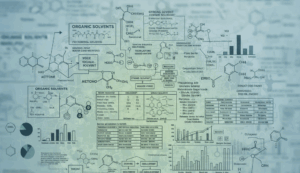
塗料と溶剤
この記事の内容
塗料分野における溶剤についての記事です。
概要、定義、法的な定義、種類をまとめています。
他サイトであまり解説されていない部分や、塗料と直接かかわる部分を中心に徒然と記載します。
個別の溶剤の性質や、シンナーの分類などについて他サイト等を案内します。
その点ご承知おきください。
溶剤とは
溶剤とは他の物質を溶解させて均一な溶液を作る液体です。より厳密にいえば特定の物質を溶かし、その成分を均一に分散させる働きを持つ液体全般を指します。
下記にJIS K 5500 塗料用語 から抜粋、引用します。
溶剤
バインダーを十分に溶解し,所定の乾燥条件で揮散する単一又は混合された液体。狭義では,バインダーの溶媒をいい,ほかに助溶剤,希釈剤がある。本来は,蒸発速度の大小によって区分するが,沸点の高低によって,高沸点溶剤・中沸点溶剤・低沸点溶剤に分けることもある。
身の回りで、もっとも代表的な溶剤は水です。塗料でも、水系塗料の溶剤は水ということになります。
溶剤は、大きく分けて有機溶剤と無機溶剤に分かれます。
無機溶剤の代表例が水であり、そのほかにフッ化水素(HF)なども洗浄に使う場合溶剤と言えますが、
塗料分野での無機溶剤は水くらいかと思います。
ただし、塗料分野の実務に限っては、溶剤と言えば有機溶剤を指します。
塗料における溶剤とは、有機溶剤系の塗料にあらかじめ含まれる溶媒であり、またそれを希釈し成分や粘度を調整するための液体(シンナー)、乾燥性などを調整する液体(リターダー)などをさします。
実務的には水は水と言えばそれで通じるため、水以外を溶剤と呼ぶのが通例となっています。
溶剤というのは、本来の定義的には水を含みますが、塗料分野の実務的には水を除いた呼称となります。
有機溶剤とは
有機溶剤の定義は炭素を含む有機化合物であり、他の物質を溶解させる性質を持つ液体の総称です。
引用元:厚労省「有機溶剤とは」※資料自体は2014年より以前のもので法令の内容が古いので注意
ただし、実際には性質だけでなく用途やその他の要素により有機溶剤と呼ばれるかどうかが決まる側面があり、また慣習的に有機溶剤と呼ぶかどうかも分かれます、そのため、分野や場面によって有機溶剤の定義は変わり、明確な定義は困難です。
下記に、表を示します。
| 項目 | 有機溶剤っぽい | 有機溶剤っぽくない |
|---|---|---|
| 主な用途 | 希釈や洗浄 | 価値の付与 |
| 構造 | 炭素中心 | 炭素あり |
| 原料 | 石油由来 | 動植物由来 |
| 揮発性 | 高い | 低い |
| 匂い | ある | 少ない |
| 沸点 | 低い | 高い |
| 引火性 | ある | ない |
| 粘度 | 低い | 高い |
| 常温 | 液体 | 固体か気体 |
見ての通り、かなり曖昧な表なのですが、実際、有機溶剤か否かは、「っぽい」「っぽくない」で判断される部分があります。
いくつか例を挙げると、「ハイドロフルオロカーボン」「リモネン」「(低粘度)シリコーンオイル」「グリセリン」「ガソリン」「シラン系モノマー」「ジメチコン」「植物油」などは、性質だけ見れば有機溶剤と言える部分がありますが、一般的にはあまり有機溶剤とは言われません(言う場面もあります)。それぞれ、いくつかの「っぽくない」要素を含んでいます。
しかし逆に、「ジクロロメタン(引火性なし)」「エタノール(自然由来)」「トリエタノールアミン(高沸点)」などは、「っぽくない」があるものの、一般的に有機溶剤と認識されています。
このように、およその傾向はあるものの、性質での定義は困難ですが、あえて言うなら、「一般的に有機溶剤と言われるものが有機溶剤」という定義が、トートロジーながら現実的には有効であったりします。
なお、有機溶剤やその分類については下記のウェブサイトも非常にわかりやすく有用です。
三協化学株式会社「有機溶剤とは?わかりやすく解説します」
法的な分類(有機則、特化則、VOC)
さて、有機溶剤全般の定義が困難とはいえ、労働者や環境保護のための規制では具体性が必要であり、法律ではリスト形式や定義として、明示的に定められております。
下記に代表的な定義を挙げます。
1.有機溶剤中毒予防規則(有機則)に定められた有機溶剤(等)
最も代表的なものは、有機溶剤中毒予防規則(有機則)です。
労働安全衛生法(労安法・安衛法)および労働安全衛生法施行令(政令)に基づく厚生労働省の省令であり、主に有機溶剤の使用に伴う労働者の中毒防止を目的とし、第1種有機溶剤(2物質)、第2種有機溶剤(35物質)、第3種有機溶剤(7物質)の合計44物質及び、それらを5%以上含む「第〇種有機溶剤等」が定められています。
以前は54物質でしたが、10物質が2014年に特化則に移管し現在の44物質になりました。厚労省のものを含め54物質となっている資料は情報が古い為、注意が必要です。
具体的な法令は下記です。
有機溶剤中毒予防規則(E-GOV法令検索)
2.特定化学物質障害予防規則(特化則)における特別有機溶剤等
また、特定化学物質障害予防規則(特化則)の特別有機溶剤等があります。
有機則と同様に、労働安全衛生法(労安法・安衛法)および労働安全衛生法施行令(政令)に基づく厚生労働省の省令であり、主に発がん性が認められた物質が定められ、有機則よりさらに厳しく管理されます。
有機則とも関連あり、2014年には有機則から特化則に10物質が移管されています。
特別有機溶剤等は、12物質及びそれらを1%以上含むものとして定められています。
具体的な法令は下記です。
特定化学物質障害予防規則(E-GOV法令検索)
3.大気汚染防止法における揮発性有機化合物(VOC)
厳密には有機溶剤の定義ではありませんが、実質的に有機溶剤の多くが該当し、また塗料分野でも非常に意識されることの多い物質群です。VOC発生源の最大分野が塗料であり、全体の実に約4割を占めます。(令和5年集計による)
こちらは大気の汚染に関して国民の健康の保護や生活環境の保全を目的とする法律であり、この中で揮発性有機化合物は下記のように定義されています。
第二条4項
この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。
具体的な法令は下記です。
大気汚染防止法(E-GOV法令検索)
ただし、この条文で定められた範囲は非常に広く、この定義のみでは実運用に向きません。
そのため、実際の運用においては下記のようなリストが使用されます。
・揮発性有機化合物排出インベントリで集計・推計される9大分類、36小分類、約500物質/分類
揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ報告書(令和6年度)
このサイトのExcelデータ2つに一覧が記載
・環境省が示す主なVOC100種
経済産業省「VOC排出抑制の手引き」参考資料1:環境省が示す主なVOC100種
また、一般にはWHO(世界保健機構)の定義
VOC「沸点範囲(常圧;50-100℃~240-260℃)の揮発性有機化学物質」
も非常に広く利用されています。
WHOの原資料がネット上で見つからないため孫引きとなりますが、下記に米国EPA引用を示します。
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/technical-overview-volatile-organic-compounds
また、下記に該当する化合物は除外されます。
https://www.epa.gov/ground-level-ozone-pollution/complete-list-voc-exemption-rules
日本塗料工業会ではVOCについてWHOの定義の一部を採用しています。
https://www.toryo.or.jp/jp/anzen/VOC/files/VOC-gl2013.pdf
本ガイドラインで対象とするVOCは塗料が対象であるため、世界保健機構(WHO)のVOC分類に基づく「沸点範囲(常圧;50-100℃~240-260℃)の揮発性有機化合物とする。
ただしこの書き方から、WHO定義の除外規定は考慮しない(沸点による分類のみを流用)と読めます。
ついでに、JIS K 5601-5-2などでは、常圧で沸点250℃未満の有機化合物をVOCとしています。
それぞれ都合があるとはいえ、なかなかにバラバラです。
さて、以上のような法律ですべての有機溶剤をカバーできるかというと、やはり不可能です。
・有機則の有機溶剤(等)・特化則の特別有機溶剤等
→あまりに数が少なく、包括的でない。あくまで労安法上の義務のために区分したもの。
代表的な有機溶剤であるベンゼンが特化則の特別有機溶剤等ではなく特定第2類物質とされていることからも、有機溶剤全般を示すには使えない。
また、これは私見ですが、エタノールが除外されている、毒性や揮発性に見合わずガソリンが第3種に分類されているなど、純粋な化学物質の性質だけでなく、現場運用の都合が考慮されているように見えます。
・大気汚染防止法における揮発性有機化合物(VOC)
→約500物質は包括的であり、結果的に有機溶剤のかなり多くの範囲をカバーしている。
ただし、このリストはやや掲載基準が不明瞭で、「オキシダントの生成の原因となる」が主目的でありながら、
通常はオキシダント生成の原因となると考えづらい物質(例:ジクロロメタンやHFC)がリストされていたり、
逆に、WHO定義のVOCに該当し、間接的にオキシダントの原因となりうるにもかかわらず
記載されていない分野(例:アルコキシシラン)もあり、やや立ち位置が不明瞭な部分は否めなません。
逆に、WHOの定義では「オキシダントの生成の原因となる」がやや厳格な目的として存在し、ジクロロメタンやHFCはもちろん、アセトンや酢酸メチルが除外されるなど、定義とその目的は明確ながら、有機溶剤という括りとはかなり異なってきます。
このように一般的な有機溶剤と法的な有機溶剤や揮発性化合物の範囲は中々一致しません。
しかし、ここまで書いておいて話をひっくり返すようですが、
塗料実務における溶剤(有機溶剤)はWHOの沸点定義のみでほぼカバーできます
※WHOの除外規定は無視
沸点で分けるのはある程度合理的で、定義として有機溶剤として使える沸点の高い有機溶剤を主として樹脂を溶解したり希釈することは一般的にほとんど無いと考えられます。
高沸点の油を主成分とした塗料や、機能性付与に高沸点の有機溶剤として使える物質を添加することはありますが、これは溶剤としての利用ではありません。
ちょっと微妙なラインとして、リターダーがあり得る程度でしょうか。
日本塗料工業会 揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制ガイドライン(平成16年7月)
例えばここの23ページに塗料に使用されている主なVOCである溶剤の一覧として示された表がありますが、可塑剤を除き全てWHOの沸点定義に該当します。
ただしこの表では主に機能性付与に添加されるテキサノールを有機溶剤としてみており、またWHO定義の沸点から外れる可塑剤をVOCとみているなど、やはり定義が難しいところはどうしても残ります。
強溶剤と弱溶剤
さて、有機溶剤の定義はほどほどに、塗料の話に戻ります。
これは塗料(また印刷)分野特有の言い方として、強溶剤と弱溶剤という分類があります。
一般的な説明としては、弱溶剤とは溶解力が比較的弱く、臭気や有害性などにおいてマイルドな性質を持つ有機溶剤と言えます。あるいは、脂肪族炭化水素を主成分とした混合溶剤といってもいいでしょう。
主に塗料用シンナーと呼ばれる溶剤がこれに該当し、弱溶剤系塗料の希釈や洗浄に用いられます。
そして、弱溶剤以外の溶剤を強溶剤、あるいは単に溶剤と言います。
液体の塗料は、水系、弱溶剤系、強溶剤系(溶剤系)に分類されます。
ただし、一価の低級アルコール溶剤を主溶剤とする塗料や、その特性を強調したい場合など、弱溶剤でも強溶剤でもなくアルコール系と呼称する場合があります。
上にマイルドと書きましたが、弱溶剤系塗料は製品名でもわかりやすくなっている場合が多く、
エスケー化研「マイルド」
関西ペイント「マイルド」「M」
日本ペイント「ファイン」
大日本塗料「スマイル」
スズカファイン「ワイド」
など、製品名に弱溶剤系塗料であることを示す言葉がつけられています。(ただし一部例外もあるようです)
さてしかし、強溶剤/弱溶剤は現場塗装やその塗料において非常に一般的に使われる言葉でありながら、共通した厳密な定義というものはなく、塗料用語(JIS K 5500)でも定められていません。
ただしJASS18では「弱溶剤系」が定義されており、以下に引用します。
弱溶剤系塗料:労働安全衛生法に基づく有機溶剤中毒予防規則に区分される第3種有機溶剤等を溶媒の主成分とした塗料
おそらく文中の「第3種有機溶剤等」は、有機則に定められた「第3種有機溶剤等」でなく「第3種有機溶剤など」という意味と思います。
定義としては「など」の幅が大きくやや不明瞭ですが、弱溶剤とはいえ第2種有機溶剤等ということもありえますし、第3種有機溶剤が主でも強溶剤となる可能性も想定できるため、このあいまいさは仕方ないでしょう。
しかし、これも同じように話をひっくり返すようですが、
塗料実務における「弱溶剤系塗料」は、製造者が「弱溶剤系塗料として販売しているもの」です
心情的には「塗料用シンナーで希釈可能な塗料」としたいところではありますが、希釈しない弱溶剤系塗料も存在し、また芳香族が入った塗料用シンナーでしか希釈できない製品も多くあり、身もふたもないですが、実務上は上記のような定義が有用です。
無溶剤
また、溶剤と弱溶剤のほかに、無溶剤という分類があります。
溶剤も弱溶剤も(ほぼ)含まないという意味ですが、これもいくつかの種類があります。
・粉体塗料
溶剤をほぼ含まないので無溶剤といえます。
・塗料液と硬化物がほぼ同一重量となるウレタン樹脂塗料やエポキシ樹脂塗料
塗料液として無溶剤であり、理想的に反応すれば完全に無溶剤と言えるでしょう。
・乾性油などを主成分とし酸化重合で硬化する油性塗料で溶剤混合のないもの(いわゆるニスなど)
乾性油と他の溶剤の混合品が一般的であるため、全てが該当するわけではありませんが、ほぼそれと顔料のみで構成された場合は、油性でありながら無溶剤ともいえます。ただし、弱溶剤での希釈を前提として弱溶剤系として扱われることもあります。また硬化する際の反応でVOCを放出します。
・含浸材や無機塗料においてケイ素化合物がほぼ100%となる塗料
理想的には無溶剤です。ただし不純物(副生成物)としてエタノールやメタノールが含まれる場合があることと、硬化する際にVOCを放出します。
・水系塗料であり、かつ溶剤をほぼ含まない
これも無溶剤と称する場合があります。
水系塗料なのだから無溶剤で当たり前で、単に水系といえばいい……と思うかもしれませんが、
実際は水系塗料でも数%の有機溶剤が含まれるケースはむしろ通常です。
環境省 すぐにできるVOC対策(平成19年3月)
例えばこの資料においても、水系塗料について「VOCは7%以下」で「VOCの組成はアルコール系他」と記載があり、無溶剤とは言えません。
※なお、ここでいう「アルコール系」は、グリコールなども含む定義と考えられます。
日本塗料工業会 環境配慮塗料の種類と内容
では無溶剤塗料をVOC1%未満としており、水系塗料においても同水準である
W1 VOC含有が1%未満の水系塗料,芳香族炭化水素が0.1%未満
が無溶剤と言えるラインかと思います。
このように、無溶剤と言っても名実ともに無溶剤であるものから、ちょっと微妙なものまであります。
また、無溶剤の定義が1%未満とされている部分について、多いと思う人もいるかもしれません。
実際どういうプロセスで1%という水準になったかはわかりませんが、
・VOCであるものとそうでないもの境がやはり明確でない
・副生成物を含め、設計上どうしても多少は入ってしまう
などから、記者としてはある程度妥当な数字かなとは思います。
ノンアルコール飲料(微アルコール)や、ゼロカロリー(厳密にはゼロでない)みたいなものですね。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
塗料分野における溶剤について、その概要、定義、法的な分類、種類をまとめました。
結論としては、塗料において溶剤というのは厳密な定義がなく、しかし複数の定義の組み合わせでおよその共通認識はあり、そのうえで運用されている、というところです。
当サイトの趣旨と違い、具体的な規格と関連する話題ではないですが、塗料にフォーカスを当てた記事があまり見当たらない話題については、このような記事も書いていく予定です。
免責事項
この記事は記者の調査または知見に基づき、その内容には正確を期しておりますが、
「ここ間違ってるよ」「こんな問題が考えられるよ」といったことがあれば、
お気軽にお問い合わせフォームからご指摘ください。
公開日 2025/9/21
最終更新2025/12/21